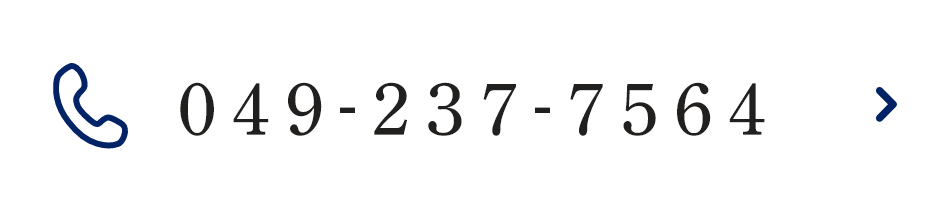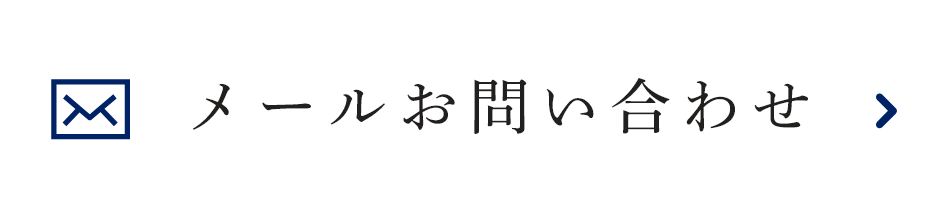ブログ
2022年1月7日 金曜日
歯の寿命と身体の寿命の関係

あけましておめでとうございます。院長の内山です。
お正月休みも終わり、
すでに学校やお仕事といった
日常生活に戻りはじめた方も多いかと思いますが
たくさん休んで、たくさん食べ、
元気になった体で
この一年を健康に過ごしましょう!
さて、そんなお正月といえば、
皆さんのご家庭で「おせち料理」はご用意されましたか?
おせち料理に使われる食材には、
それぞれに「おめでたい意味」や、
「縁起をかついだ長寿の願い」などが込められており、
昔から多くの人々が
健康に長生きできるように願っていた
というのがよくわかりますね。
ところで、
そんな「身体の寿命」とは別に、
「歯」には「歯の寿命」がある
というのはご存じでしょうか。
実は、私たち人間は
80歳を迎えるまでに
たくさんの歯を失ってしまうため、
生涯自分の歯だけで食事を楽しめる人は
ごくわずかなのです。
そこで今回は、
そんな「歯の寿命」と、
それを延ばすための方法について
ご紹介させていただきます。
◆歯を○○歳まで長生きさせよう!
歯の寿命は人間の寿命よりも短く、
皆さんの年齢や健康状態に関わらず
歯が抜け始めてしまう可能性はゼロではありません。
しかも、歯の本数が減ってしまうと、
日々の食生活はもちろん、
コミュニケーションや
運動能力にも影響が及ぶなど、
身体にも様々な悪影響があらわれはじめます。
つまり、
歯の有無は全身の健康に関係するため、
皆さんの健康・寿命と
歯の健康・寿命は
異なるようで密接な繋がりがある
ということなのです。
このことから、
厚生労働省と日本歯科医師会は
とある目標を提唱しています。
ずばり、その目標とは
80歳まで20本の歯を残すこと
=8020(ハチマルニイマル)運動です!

◆「歯」が減れば「食べられるもの」も減る
私たちは日頃、
お肉やお餅のように歯ごたえのあるものや、
おせんべいのような硬いものなど、
実に様々な食べ物を口にします。
しかし、歯の本数が減ってしまうと
それらをうまく噛み砕けなくなってしまうため、
食べものが喉に詰まる原因になることも。
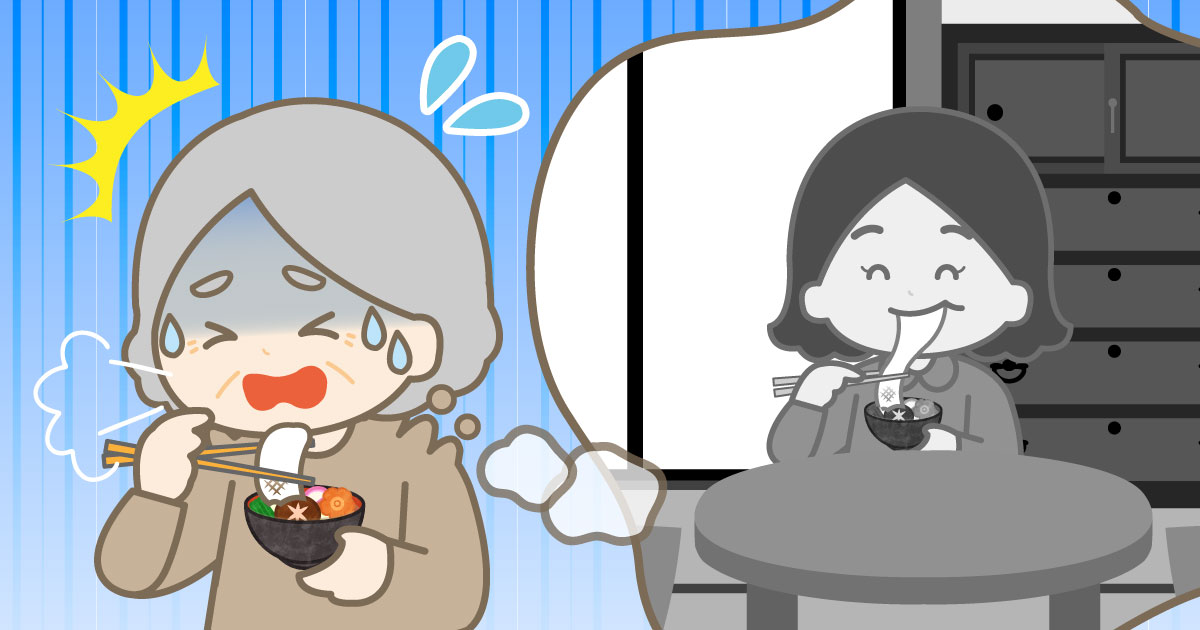
そう、これまで
「おいしく食べられた料理」が一転して、
「命を脅かす危険な食べもの」に
変わってしまうのです。
◆豊かな人生は健康なお口から
日本人の平均寿命は
男女ともに80歳を超えるようになり、
これからも延び続けることが予想されています。
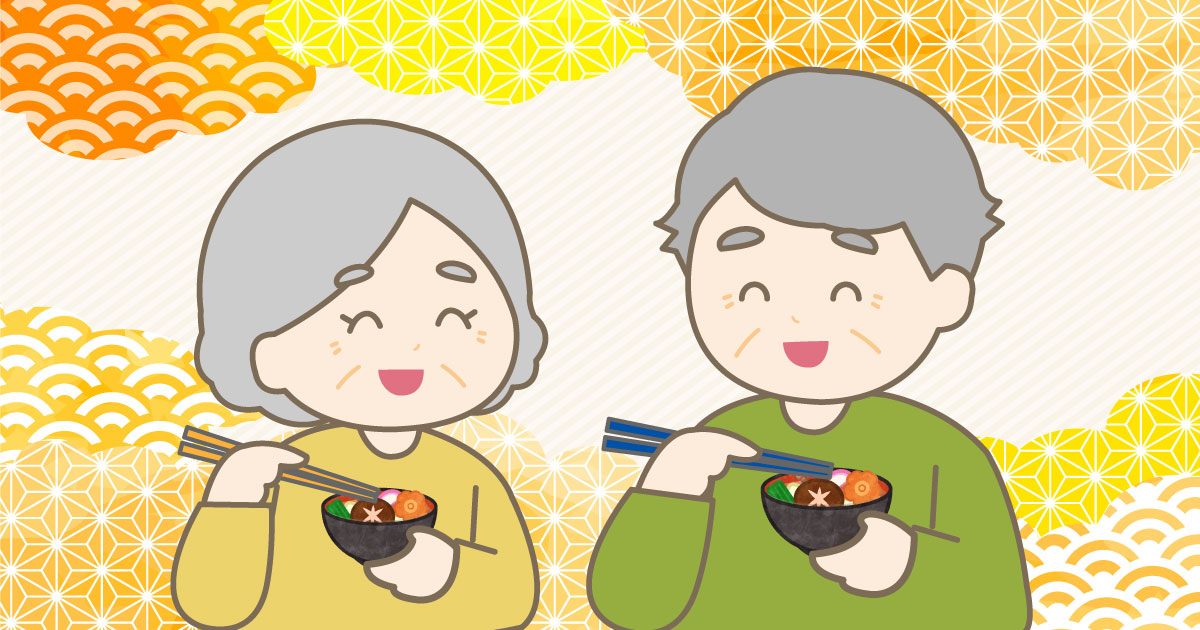
しかし、せっかく寿命が延びても、
その時間を豊かに過ごせなくては
もったいないと思いませんか?
つまり、身体だけではなく
歯をより多く残し、
お口の健康を保つことが
重要になってきます。
それには歯の喪失の原因…
「むし歯」や「歯周病」などの
予防・早期発見・早期治療が
必要不可欠です。
特に歯周病は、
別名「沈黙の病」と呼ばれるほど、
自覚症状の乏しい病気。
気づいた頃には重症化していることも
少なくありません。
そのためにも定期検診は欠かさずに、
何か気になることがあれば
すぐに相談するようにしましょう。
皆さまの歯と健康を守るために、
常に最善の診療を心がけて参りますので
2022年もどうぞよろしくお願いいたします!
さくらの山歯科クリニック
〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F
TEL:049-237-7564
URL:http://www.sakuranoyama.jp/
Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE
投稿者 | 記事URL
2021年12月27日 月曜日
知らぬ間に骨が溶ける?喫煙者のお口リスク

こんにちは。院長の内山です。
年末年始の準備でバタバタと忙しいこの季節。
その中でも、恐らく皆さんも行う大掃除ですが、
もともとは12月13日になると行われていた
「すす払い」という行事が由来となっており、
「正月事始め」の一環として
新年を迎えるための習慣だったそうです。
そんな年に一度の大掃除ですが、
実際には日頃からこまめに掃除をしていれば、
手間も時間も少なく済みます。
そしてそれは、歯のお掃除も同じこと。
実は、普段からお口の中をきれいな状態にできていないと、
お口の中の細菌がどんどん増え
『歯周病』や『むし歯』のリスクが確実に高まります。
特にタバコを吸う方は、
『歯周病』に対して十分な注意が必要です。
そこで今回は、
タバコとお口の関係についてお話したいと思います。
◆気づいたときにはもう手遅れ
歯周病を「ただ歯ぐきが腫れるだけの病気」
と考えている方がいらっしゃいますが、
それは大きな間違いです。
歯周病は
歯と歯ぐきの間に歯周病菌が入り込み、
腫れや出血を伴いながら、
やがては歯を支える骨を溶かしてしまう
恐ろしい病気です。
骨が溶けてしまうと、
当然それに支えられていた歯は抜けてしまいます。
実は、歯が抜けてしまう原因のNo.1は、
「むし歯」ではなく
「歯周病」なのです。
歯周病で歯を失う原因としては
「自覚症状の少なさ」が挙げられます。
唯一とも言える自覚症状は「歯ぐきの出血」。
もし、出血がいつまでも続いているようだと、
歯を支えている骨が溶け始めている可能性が高いので、
今すぐにでも歯科に相談してください。
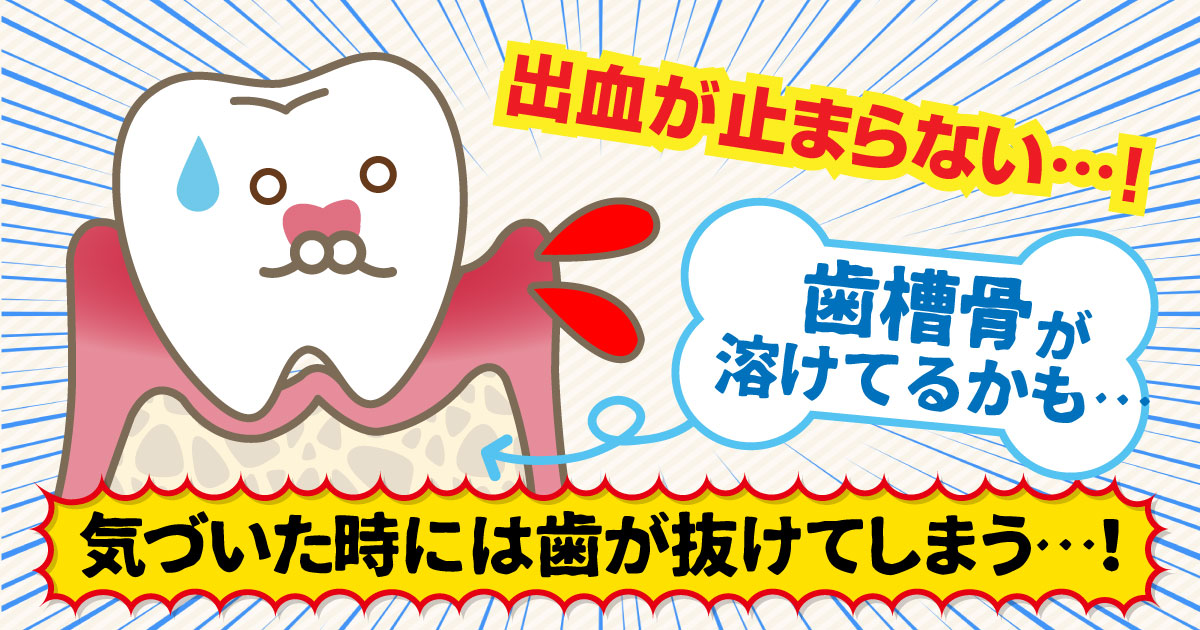
ところが、
そんな唯一の自覚症状とも言える
「出血」すら気づかなくさせるのが「タバコ」です。
タバコに含まれる有害物質は、
歯ぐきの血流悪化を引き起こし、
出血しにくくなるため
歯周病に気づきにくくなってしまうのです。
それだけではありません。
血流が悪いということは、
細菌と戦う力が衰えることを意味しますので、
歯周病菌がどんどん増えていきます。
「ようやく気づいたころには、
もう骨がすっかり溶けてしまっている」
喫煙者にはこうしたリスクがあることを
しっかり覚えておいてください。
◆全身疾患につながる可能性も…
このように、タバコは歯周病を悪化させますが、
歯周病の悪影響は口腔内だけではありません。
歯ぐきから侵入した細菌が血管に入り、
全身にまわることで、
・心臓疾患
・脳血管疾患
・認知症
・糖尿病
・がん
・早産
・低体重児など、
様々な病気に関わっていることが知られています。
このように、タバコは肺がんや歯周病だけでなく、
全身疾患を悪化させる引き金になり得るのです。
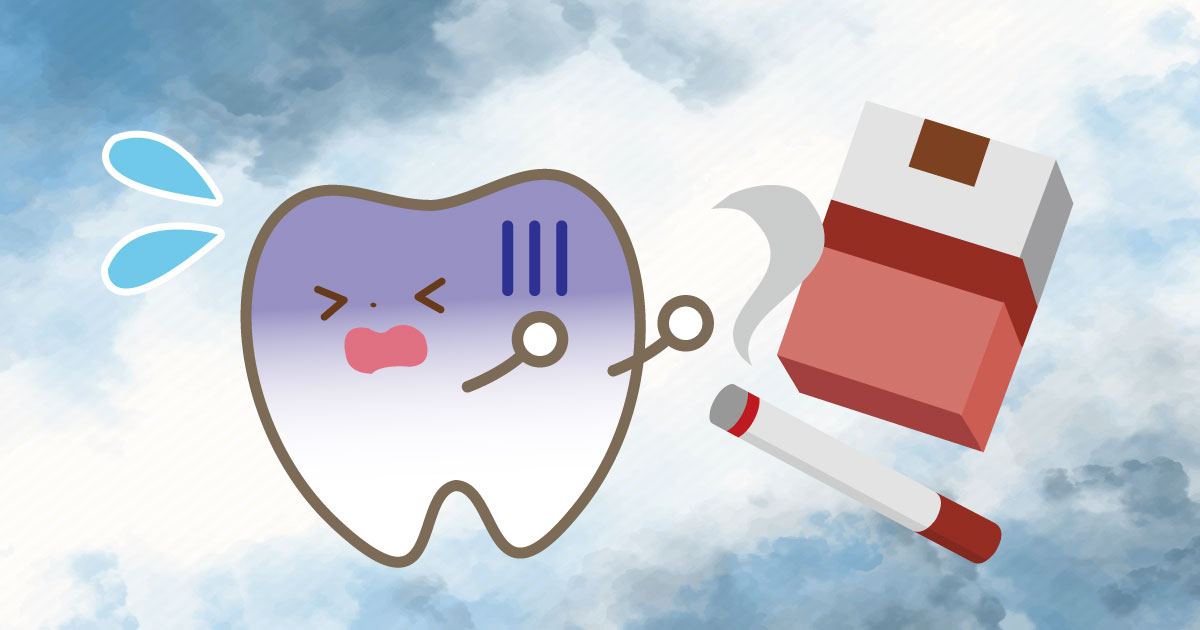
◆禁煙は歯の治療に大切なこと
「自分はもう歯周病になってしまったから
関係ない!」
と思われた方も、まだ遅くありません!
ある程度進行した歯周病にも禁煙は有効なので、
ぜひチャレンジしてみましょう。
禁煙をすると歯ぐきの状態が回復して、
歯周病のリスクが下がります。
さらに、
歯周病を予防することが全身疾患の予防になり、
ひいては健康な人生をおくることにもつながっていきます。

また、喫煙をしている方は、
自覚症状が少ないため、
必ず定期的に歯科で検診を受けてください。
検診では歯周病のチェックのほか、
歯周病菌のすみかとなっている歯石を取り除いたり、
歯にこびりついたヤニを取り除いたりすることもできます。
疾患の早期発見・予防・見た目の改善など、
様々なメリットがありますので、
ぜひ定期的なご来院をお待ちしております。
さくらの山歯科クリニック
〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F
TEL:049-237-7564
URL:http://www.sakuranoyama.jp/
Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE
投稿者 | 記事URL
2021年12月19日 日曜日
フッ素とは?[若葉、鶴ヶ島、川越の歯医者 さくらの山歯科クリニック]

こんにちは。
朝晩の冷え込みがつらくなってきました。
私の家ではこたつ、暖房器具、に活躍していただいてます!
火事にならないよう皆様も暖房器具には注意しましょう。
私も消し忘れないように注意します。
今回はフッ素について、お話ししていきたいと思います。
フッ素とは?
食事することにより口の中は中性から酸性に傾きます。
簡単に言うと歯を溶かす脱灰と言う現象が起こります。
フッ素は、歯の脱灰を抑制し、なおかつ歯を強くする再石灰化を促進してくれます!
そして、虫歯菌の活動も抑制する作用も有るそうです。
海外では水道にフッ素(フッ化物)を添加し、多くの住民を対象として虫歯を予防する方法とされてるようです。
虫歯予防を出来る方法
手軽に毎日出来る事は、
高濃度フッ素歯磨き粉を使用して歯を磨く事です。
ここで注目なのが高濃度!
歯磨き粉はいろいろなメーカーさんが出していますが、皆さんはフッ素の濃度を考えて購入した事が有りますか?
日本の薬事法では1500ppmまでフッ素を入れても良いことになっています。
濃度に関係いなくフッ素が入っていれば記載はフッ素含有となる訳ですが、、、
どのくらい入っているかわからない歯磨き粉は正直多いです;
自信をもって入れてるメーカーさんの歯磨き粉には必ず記載がありますので
確認してみてください!
また、高濃度フッ素を入れているメーカーさんは発泡性と言う、
泡が立つのを少なくしています。泡が立つとうがいの回数が多くなってしまいます。
そうすると、せっかくのフッ素が流れてしまい効果の持続が無くなってしまいます。
持続性を高めるために、うがいの量、回数を気をつけてみて下さい。
プラスアルファで、、、
フッ素洗口液で口をすすぐ事も出来るとさらに良いです!
夜歯を磨いた後に、フッ素配合の洗口液でフッ素をすみずみにまで行き渡らせます。
使った後に水ですすがないので、口の中でフッ素が留まります。
毎日の事に取り入れ歯を強くしていきましょう!
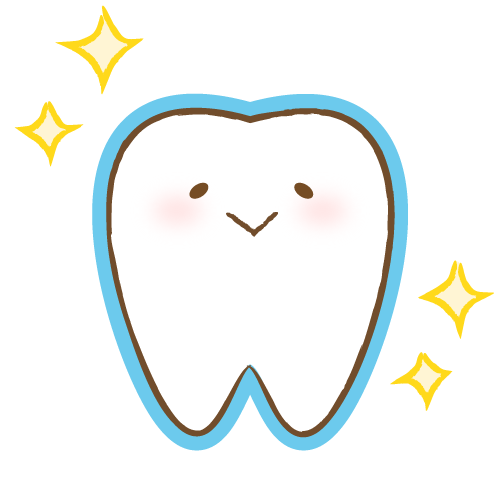
皆様のご来院、スタッフ一同心よりお待ちしております。
投稿者 | 記事URL
2021年12月5日 日曜日
知覚過敏
こんにちは。
12月になり寒さが厳しくなってきましたね。
コロナも新たな変異株の感染のニュースが増えていますが、引き続き体調管理に気を付けて、元気に過ごして行きたいですね。
歯ブラシの毛先が触れた時や、冷たい飲み物を飲んだ時、風に当たった時などにキーンとしみたり、ピリッと痛みを感じることはありませんか?
虫歯などの病変が見られない場合は、知覚過敏の可能性があります。
歯の表層にあるエナメル質は、神経がないので痛みを感じることはありません。エナメル質の内部には象牙質があり、さらにその内部には歯髄(歯の神経)があります。
エナメル質が何らかの原因でなくなり、その下にある象牙質が露出することで、しみたり痛みを感じます。
⚫︎原因
・歯周病などにより歯肉が下がる
・歯の破折
・歯ぎしりくいしばりなどにより歯がすり減る
・間違ったブラッシング方法(強いブラッシングや硬すぎる歯ブラシなど)
・食べ物や飲み物に含まれる酸により歯が徐々に溶けてしまう
⚫︎治療方法
・知覚過敏用の歯磨き剤を使用する
・知覚過敏用の薬剤塗布
・コーティング材の塗布
・歯周病の治療
歯周病になると歯肉が下がったり、歯肉の炎症により歯肉
が引き締っていないことで象牙質が露出し、知覚過敏症状
が出やすくなる。
・レジン修復
プラスチックの樹脂を貼り、象牙質をカバーする。
・マウスピース作製
歯ぎしりくいしばりによる歯にかかるダメージを
軽減する。
・噛み合わせの調整
知覚過敏は、一時的にしみるのが特徴です。
ずっとしみていたりズキズキ痛む場合は、気付かない所に虫歯があるのかもしれません。
気になる症状がある場合は、早めの受診をおすすめします。
スタッフ一同、皆様のご来院をお待ちしております。
投稿者 | 記事URL
2021年11月11日 木曜日
新米パパ・ママ必見!妊娠中に増えるお口のトラブル

こんにちは。院長の内山です。
11月23日は年内最後の祝日、
「勤労感謝の日」ですね。
文字からすると
「働く人に感謝する日」だと思われがちですが、
実はそれは少し違います。
この日は
勤労を尊び、
生産を祝い、
国民がたがいに感謝しあう日
つまり、
「『働くこと』そのものに感謝する日」なんですね。
今年最後の祝日を、
日頃がんばっているご家族や自分へのご褒美として
ゆっくり過ごしてみるのはいかがでしょうか。
さて、そんな「勤労」といえば、
近ごろは男女関係なく仕事をしている人が多く、
なかには、妊娠中でも働くお母さんもいらっしゃいます。
しかし、妊娠中の身体には様々な変化が起こるため、
今までのようにいかないこともたくさんあります。
そしてそれはお口の中でも同じ。
皆さんも、
「妊婦さんは、むし歯や歯周病になりやすい」
といった話を聞いたことはないでしょうか?
今回はそんな妊娠中に増える、
お口のトラブルについてご紹介します。
◆妊娠中はお口のトラブルの悪循環に注意!!
妊娠すると女性ホルモンが増加します。
実は、歯周病を引き起こす歯周病菌の中には
「女性ホルモンによって活発化」するものがあり、
歯周病のリスクが増大します。
すると、歯ぐきに腫れや出血がみられるようになり
さらに、お口の中がネバネバするなど
不快な状態になることが少なくありません。
また、ホルモンバランスが乱れると
「妊娠性エプーリス」という病気になり
歯ぐきに「できもの」ができることもあります。
これらはいずれも、
「痛み」や「出血」を伴うため、
歯みがきしづらくなります。
すると、
お口の細菌がどんどん増えることになり、
歯周病がさらに進行して、
もっと腫れや出血がひどくなる…。
こうした悪循環になってしまうのです。
もちろん、細菌が増えれば歯周病だけでなく
むし歯の危険性も高まります。
◆母体だけじゃない!
歯周病は赤ちゃんにも影響が…
さらに、歯周病はお口の中のトラブルに留まらず、
赤ちゃんにも影響を及ぼします。
歯周病はお口の中だけでなく、血管内に細菌が入り込んで
全身に影響を及ぼします。
実は、妊娠中に歯周病になると
「低体重児・早産のリスク」が高くなる
ということが明らかになっているのです。
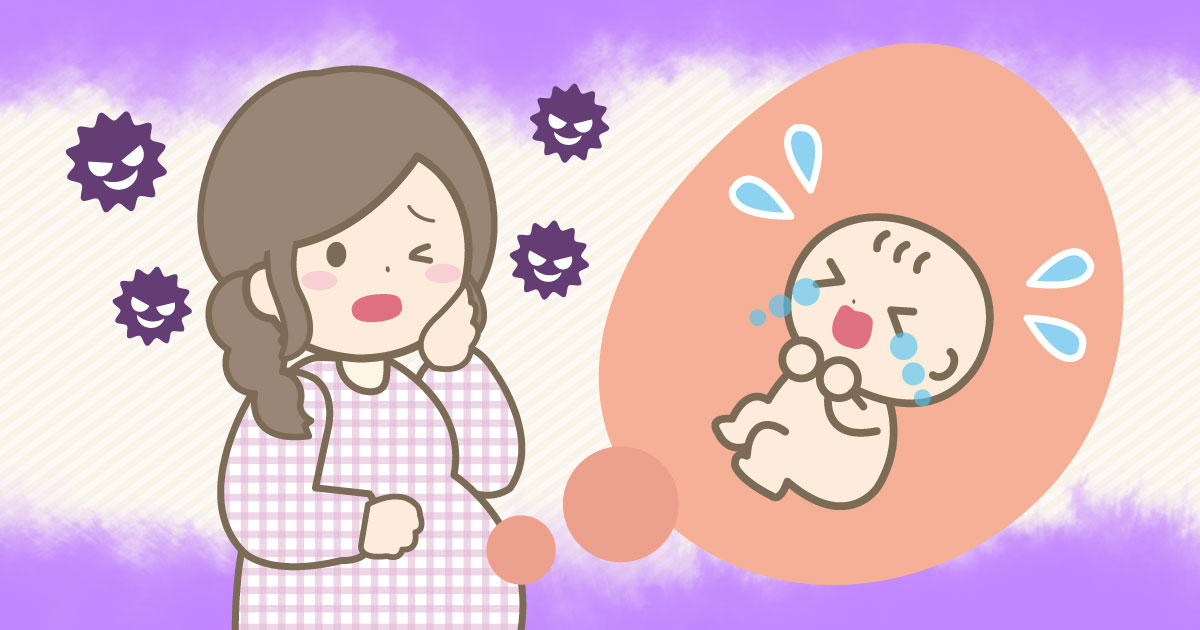
日々の歯みがきは、歯周病予防の基本!
ですが、
妊娠中はつわりがひどいと
歯みがきが難しいこともあります。
そんな時は、
・歯みがき粉の味を変える
・洗口液を使う
それも難しければ、
うがいをするだけでもいいので、
お腹の赤ちゃんを守るためにも
お口を可能な限り清潔に保つように
心がけてみてください。

◆妊娠中でも治療はできる?
妊娠中の歯科治療というと、
赤ちゃんへの影響を気にして
治療をためらうお母さんもいらっしゃいます。
しかし、病気を放置していると
お母さんのストレスが増えたり、
低体重児・早産のリスクが高まったりして、
かえって悪影響を与えることも。
そのため、しっかり治療するほうが
赤ちゃんにとってもお母さんにとっても、
確実にメリットがあります。
安定期に入れば、
ほとんどの治療を受けていただくことができますし、
麻酔やレントゲンなども
胎児にほぼ影響はありません。

また、安心してお産に臨めるよう、
妊娠初期と安定期には
歯科検診を受けましょう。
心配事などのストレスは溜め込まないように、
気になることがあればいつでもご質問ください。
さくらの山歯科クリニック
〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F
TEL:049-237-7564
URL:http://www.sakuranoyama.jp/
Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE
投稿者 | 記事URL
カテゴリ一覧
- さくらの山歯科クリニックブログ (416)
- 料金表 (1)
- 未分類 (24)
- 求人情報 (3)
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2026年2月 (2)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (4)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (2)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (3)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (4)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (1)
- 2019年4月 (3)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (5)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (3)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (6)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (6)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (5)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (3)
- 2016年6月 (3)
- 2016年5月 (5)
- 2016年4月 (3)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (5)
- 2015年11月 (5)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (3)
- 2015年6月 (3)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (3)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (3)
- 2014年7月 (3)
- 2014年6月 (4)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (5)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)