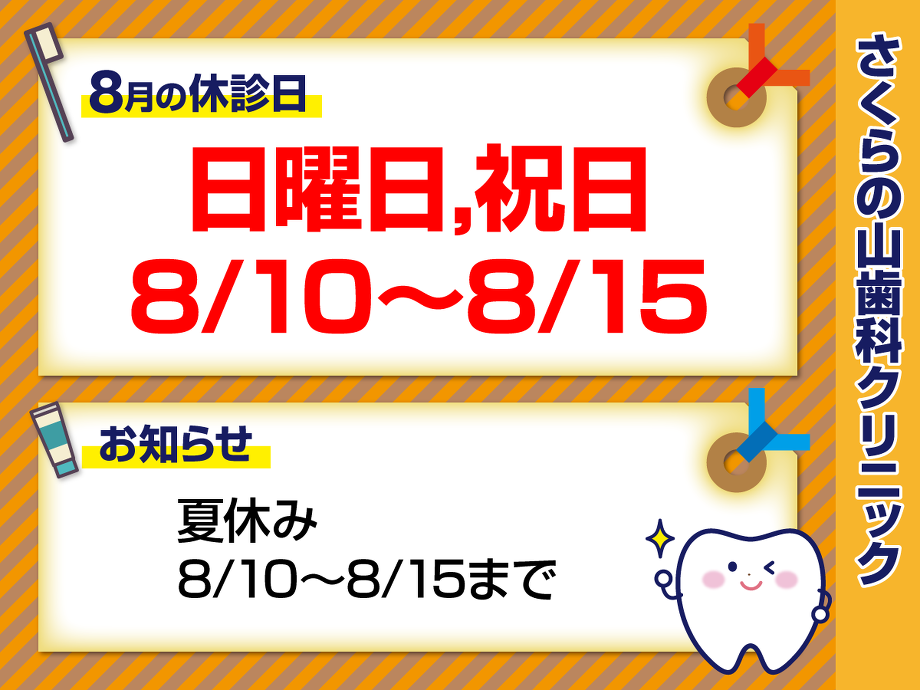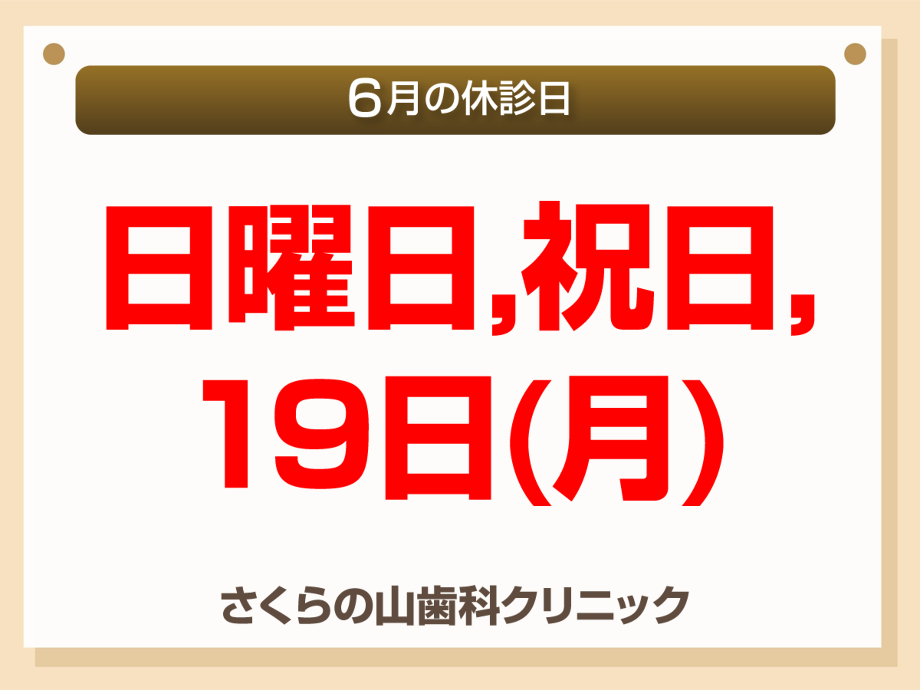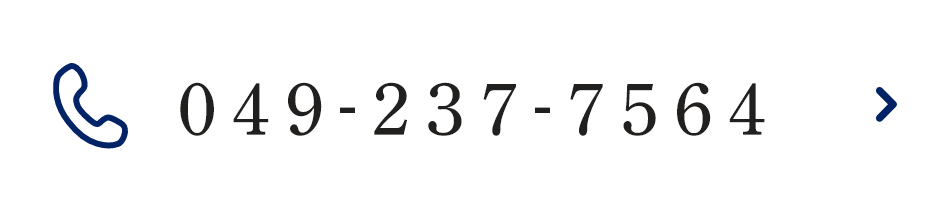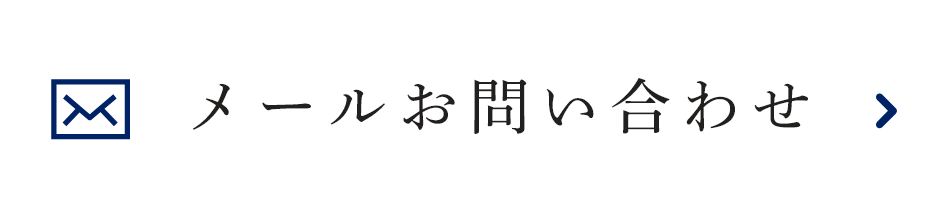ブログ
2023年7月6日 木曜日
旅行前に要対策!突然痛む「気圧性歯痛」とは?

こんにちは。院長の内山です。
7月に入るといよいよ夏本番。
旅行やキャンプ、マリンスポーツといった
レジャーがたくさん楽しめる季節です。
日ごろの疲れを癒やすべく、
お子さんの夏休みやご自身の休暇に合わせて、
計画を立てている方も多いのではないでしょうか?
しかし、そんなせっかくの「楽しみ」も
突然の「歯の痛み」に悩まされては台無しです。
むし歯や歯周病にも注意が必要ですが、
実は『気圧性歯痛(きあつせいしつう)』という、
旅行中だからこそ起こりやすい歯の痛み
が存在します。
◆飛行機に乗ると起こりやすい症状
飛行機が離陸する際や着陸するときに
「耳がつまる、痛くなる」といった症状が
出る方もいらっしゃいます。
これは、機内の気圧が変化することで、
鼓膜の内側と外側で
「気圧の差」が生じてしまうためです。
こうした
「飛行機に乗った際に起こりやすい身体の異常」は、
ほかにも「お腹が痛くなる」
「気分が悪くなる、吐き気を催す」
といったものもあり、
航空会社の案内でも注意喚起されています。
そして、そのなかには
「歯痛」もしっかりと紹介されているのです。

◆「気圧の変化」が歯痛の引き金に
飛行機に乗ると歯が痛む原因は、
耳のときと同じく「気圧の変化」です。
皆さんは、機内に持ち込んだスナック菓子が、
次第に膨らんでいくことがあるのはご存じでしょうか?
これは、飛行機の高度が上がって周囲の気圧が低くなると、
「袋の外側から抑える力」よりも、
「内側の押し返す力(圧力)」のほうが
強くなるためです。
実は、「飛行機に乗ると歯が痛む理由」も
これと同じです。
歯の内側には
「歯髄腔(しずいくう)」という
神経の詰まった空洞があります。
気圧が下がるとスナック菓子の袋と同じように、
内側の圧力のほうが強くなり、
歯の痛みを引き起こしてしまうのです。

このような気圧の変化によって生じる歯痛を
『気圧性歯痛』といい、
飛行機だけではなく、登山やダイビングなどでも
起こりやすいと言われています。
◆楽しい旅行やレジャーの前に歯科でチェック!
特に、むし歯や治療中の歯は、
気圧性歯痛が発生する可能性が高くなります。
もし、これから旅行やレジャーへ行くにも関わらず、
治療が必要な歯や、治療中の歯を放置している方、
また「しばらく歯科を受診していない」という方は、
楽しい思い出を作るためにも、
事前に歯科で検診を受けておくことを
おすすめいたします。

当院では、
皆さまのお口に関するお悩みを解決できるよう
スタッフ一同、全力で治療に取り組んでいます。
「旅行前に治療を終わらせたい」などのご希望があれば、
精一杯サポートさせていただきますので、
いつでもお気兼ねなくご相談ください。
さくらの山歯科クリニック
〒350-2203
埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F
TEL:049-237-7564
URL:http://www.sakuranoyama.jp/
Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE
投稿者 | 記事URL
2023年6月6日 火曜日
油断大敵!磨きすぎ?「くさび状欠損」とは

こんにちは。院長の内山です。
季節柄どうしても雨模様が続き、
お出かけもしにくいこの時期は、
心も身体も滅入ってしまいがちです。
そのようなときこそ、
ストレッチやエクササイズで身体を動かし、
読書や音楽鑑賞などで気分をリラックスさせ、
心身ともに健康を保つことが重要です。
それに加え、6月4日から10日は、
『歯と口の健康週間』でもありますので、
ぜひ「お口の健康」にも気を配ってみてくださいね。
さて、そんな「お口の健康」のために
欠かせないことといえば、毎日の歯みがき。
しかし、「薬も過ぎれば毒となる」とあるように、
歯みがきもあまり頑張りすぎると、
思わぬトラブルを招くことがあります。
◆これってむし歯?
歯がしみるのは「くさび状欠損」かも!
毎日きちんと歯を磨いているにもかかわらず、
「冷たいものが歯にしみる」
「歯ブラシを当てると痛い」
と、感じたことはありませんか?
その要因のひとつとして考えられるのが、
『くさび状欠損』です。
皆さんは「くさび」というものをご存じでしょうか?
建築などで用いられる
「V字型の部品」のことなのですが、
それにたとえて、
「くさびが打ち込まれたように
歯と歯ぐきの境目が欠損している状態」のことを、
『くさび状欠損』といいます。
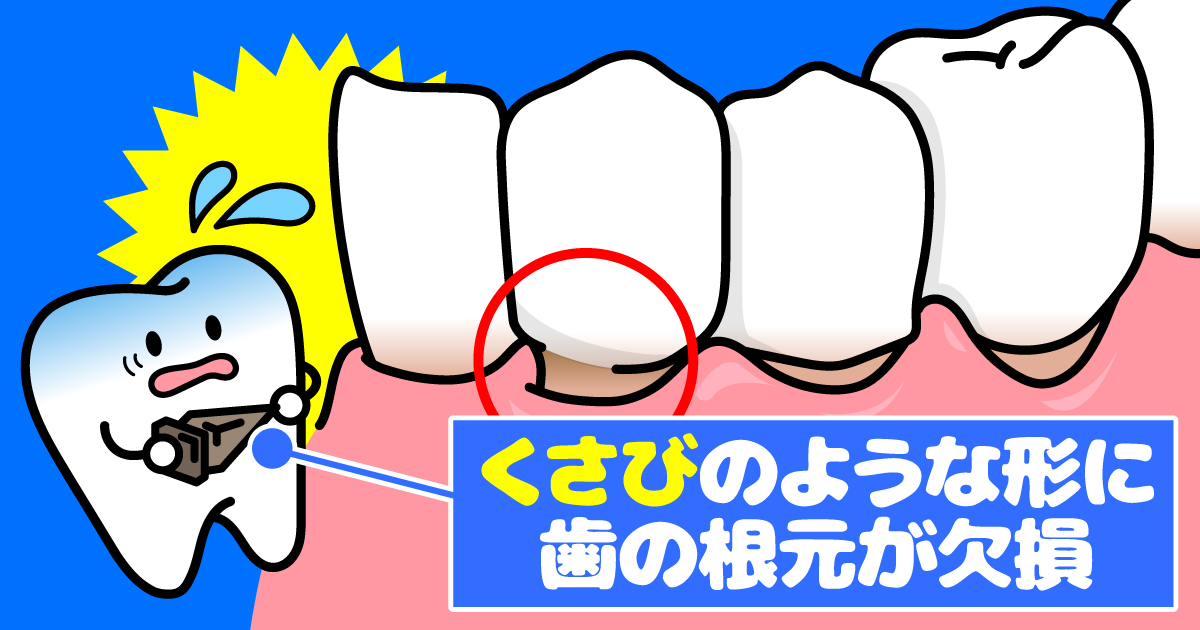
歯の根元を触った際に段差を感じる場合、
くさび状欠損の可能性は高くなります。
違和感こそあるものの、
初めのうちは「痛み」や「しみる」といった
自覚症状がないため、
気づかずにそのまま放置してしまうことも
少なくありません。
症状が進行すると、
「冷たいものが歯にしみる」
「歯ブラシを当てると痛い」
といった症状が表れるほか、
プラークが溜まって
むし歯や歯周病になるリスクが上がります。
◆歯みがきには「いい加減」が大切
くさび状欠損が生じる原因として
意外と多いのが「過度なブラッシング」、
つまり、「歯の磨きすぎ」です。
たとえば、
・力を入れて歯をゴシゴシ磨いてしまう
・しっかり磨けるように硬い歯ブラシを使っている
・1日に何回も歯を磨く
など、特に「歯みがきに熱心な方」ほど、
その傾向に陥りやすいです。
また、「歯ぎしり」や「食いしばり」などによって、
強い負荷が加わり続けると、
その力が根元に集中して、
歯の表面に細かなヒビが入り、
くさび状欠損が生じてしまうこともあります。

◆くさび状欠損が大きくなる前に!
早めに受診を
くさび状欠損は、
歯科用の樹脂を詰めることで、
しみるのを軽減させつつ、
見た目も綺麗にすることができます。
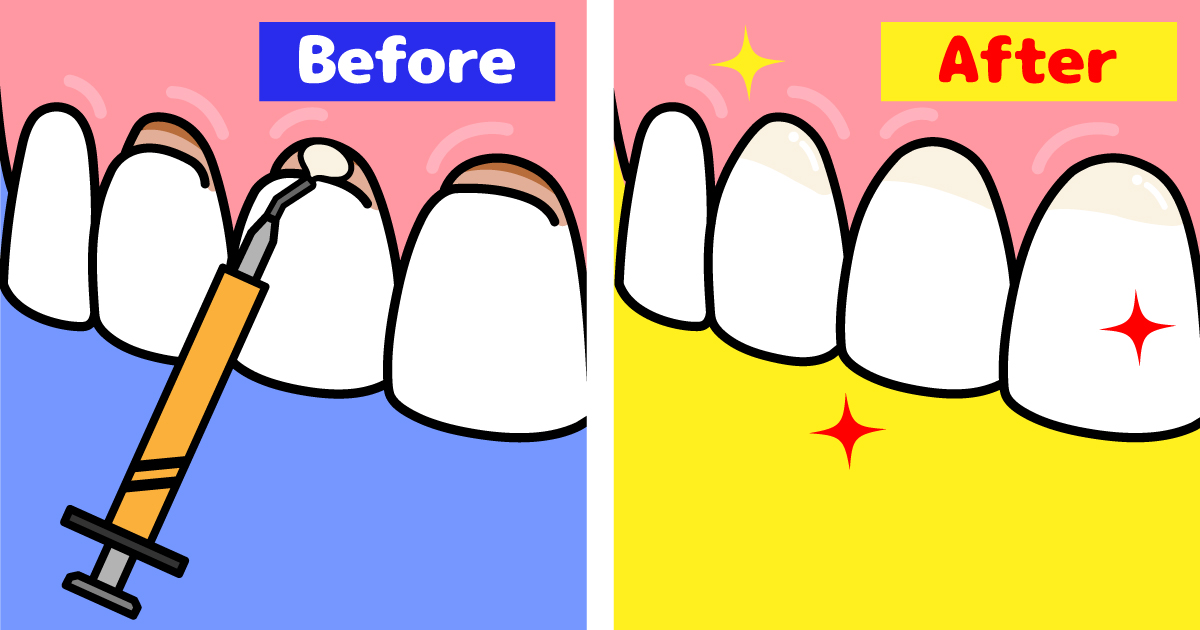
しかし、ブラッシングや歯ぎしりなど、
原因となる日々の習慣を解決しない限り、
せっかく樹脂を詰めてもすぐに剥がれ落ち、
くさび状欠損が更に大きくなるばかりです。
そのためにも、まずは
「ブラッシング法や歯ブラシの選び方を見直す」
「歯ぎしり用マウスピースを着用する」など、
原因に対するアプローチが重要です。
歯科医院では、皆さまの症状に合わせた、
最適なアドバイスをすることができます。
原因や対処法についてのご相談など、
いつでもお待ちしておりますので、
症状が悪化する前に、
早めの受診を心がけてくださいね!
さくらの山歯科クリニック
〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F
TEL:049-237-7564
URL:http://www.sakuranoyama.jp/
Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE
投稿者 | 記事URL
2023年5月8日 月曜日
「治療の中断」は絶対厳禁!

こんにちは。院長の内山です。
暖かな日も増え、
キャンプやピクニックなどの
レジャーを楽しむ方も多いかと思います。
しかし、アウトドアは
天候に左右されてしまうため、
予定していた計画が中止になってしまった…
というケースも起こり得ます。
こうした「予期せぬ中断」が起こると、
楽しい気分も台無しになってしまいますよね。
実は、歯科においても『中断』が
皆さんの「不幸」につながってしまう
場合があります。
それは、歯科治療の中断です。
◆リスク1.治療が長引く
むし歯の治療を進めていくと、
「仮詰め」や「仮歯」といった処置を行う場合があります。
これらは、文字通り
ちゃんとした「つめもの」「かぶせもの」を作っている間、
患部を塞いでおくための仮のもの。
すぐに外す前提のため、
外れやすく、材質も脆いので
すき間が生じやすくなっています。
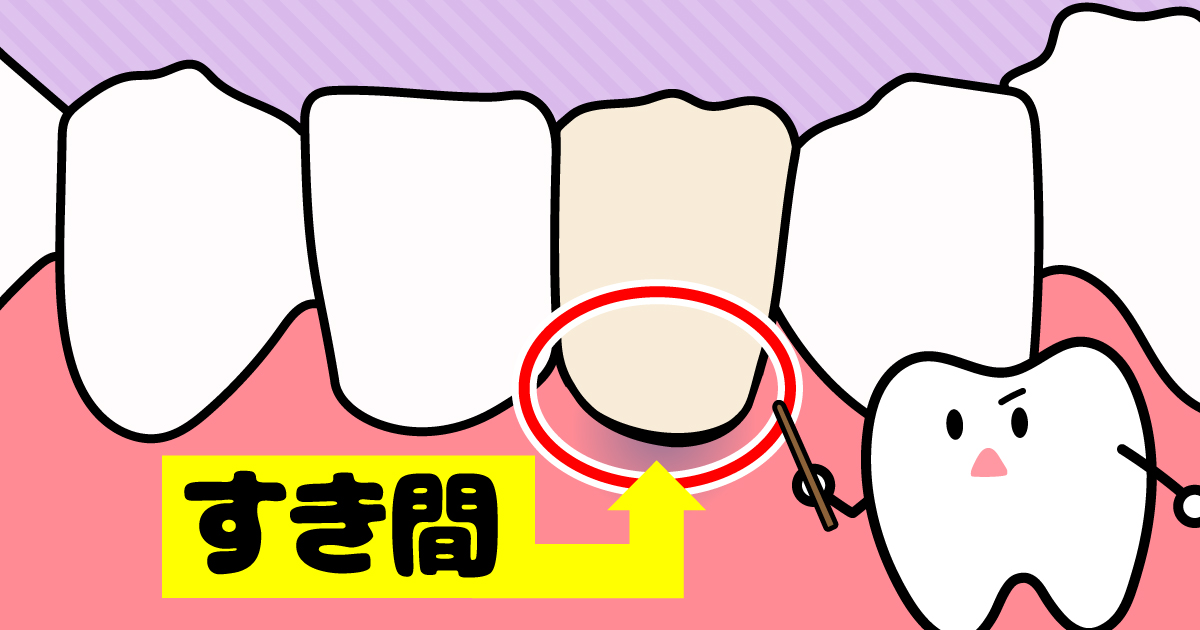
「もう痛くないから」と、
自己判断でうっかり通院を止めてしまうと、
むし歯が再発する場合や、
治療開始時より悪化してしまう、
ということもしばしばあります。
また、「型取りを終えたあと」の中断にも注意が必要です。
あまり長く放置すると、再び型取りをして
つめものやかぶせものを
新しく作り直さなくてはならない場合もあるため、
無駄に治療期間が延びてしまうことになります。
◆リスク2.歯の寿命が短くなる
治療の中断には、
「歯の寿命が短くなる」というリスクもあります。
たとえば、仮歯や仮詰めをしたところは
細菌が溜まりやすく、中断して放置すると
新たなむし歯ができてしまいます。
特に、むし歯が神経にまで達してしまうと、
神経をとらなくてはならず、
歯の寿命が著しく短くなります。
また、神経をとり除いた後などに行う
「歯の根の治療」の中断も注意が必要です。
むし歯になりやすいだけでなく、
根っこが弱くなっているため、
割れたりヒビが入ったりしやすくなります。
そうなってしまうと
「抜歯」せざるを得なくなることが多いため、
「歯の根の治療」は必ず最後まで受けましょう。

そして、「歯周病治療の中断」も
歯の寿命に大きな影響を及ぼします。
歯周病は、進行すると
歯を支えている骨が溶けてしまう恐ろしい病気です。
その原因が「歯周病菌」であり、
すみ家となっているのが『歯石』です。
そのため歯周病の進行を食い止めるために、
「歯石の除去」を行っていきます。
しかし、治療を中断してしまうと、
何百億という細菌が、
歯石に隠れて増殖しながら歯を支える骨を溶かし続け、
やがては歯が抜け落ちてしまうのです。
◆リスク3.治療費が高くなる
リスク1、リスク2からもわかるように
治療を中断すると、治療のやり直しや、
さらなる悪化の原因となります。
それによって当然、
時間も治療費も余計にかかってしまいます。

中断せずに
最後までしっかり通院することで得られるのは、
歯の健康だけではありません。
貴重な時間を無駄にせず、
経済的な負担を抑えることにもつながるのです。
むし歯や歯周病といったお口の病気は、
放っておいても自然に治る病気ではありません。
誤った状態で放置すると、
確実に悪化します。
私たちが
「治療は終わりました」とお伝えするまで、
欠かさず通院を続けてください。
もし、急用などで
やむを得ず来院できないときには、
必ずご相談ください。
皆さまの大切な歯を残すため、
私たちが全力でサポートさせていただきます!
さくらの山歯科クリニック
〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F
TEL:049-237-7564
URL:http://www.sakuranoyama.jp/
Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE
投稿者 | 記事URL
カテゴリ一覧
- さくらの山歯科クリニックブログ (416)
- 料金表 (1)
- 未分類 (24)
- 求人情報 (3)
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2026年2月 (2)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (4)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (2)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (3)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (4)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (1)
- 2019年4月 (3)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (5)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (3)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (6)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (6)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (5)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (3)
- 2016年6月 (3)
- 2016年5月 (5)
- 2016年4月 (3)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (5)
- 2015年11月 (5)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (3)
- 2015年6月 (3)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (3)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (3)
- 2014年7月 (3)
- 2014年6月 (4)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (5)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)