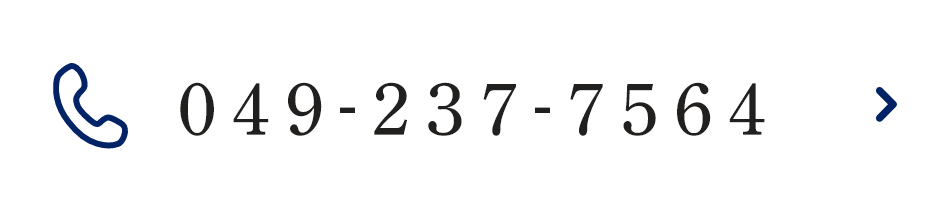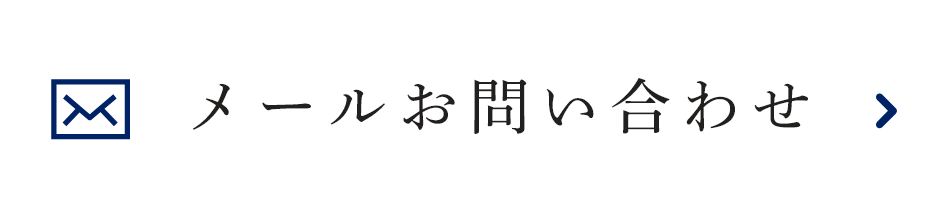さくらの山歯科クリニックブログ
2025年5月20日 火曜日
入れ歯が外れる!その原因と対処方法を解説!
こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

入れ歯を使用していると「話しているときに外れる」「食事中にずれる」といったトラブルに悩まされることがあります。入れ歯が安定しないと、食べることや話すことに支障をきたすだけでなく、精神的なストレスにもつながりかねません。
このような問題には、入れ歯の形状や噛み合わせ、使用年数、口腔内の変化など、さまざまな原因が関係しています。
この記事では、入れ歯が外れる主な原因と適切な対処方法についてわかりやすく解説します。
入れ歯が外れる原因

ここでは、入れ歯が外れる主な原因について詳しく解説します。
顎の骨の痩せによるフィット感の低下
入れ歯は、歯を失ったあとの顎の骨や歯茎の形に合わせて作製されます。
しかし、歯を失った部分の骨は時間とともに少しずつ吸収され、痩せていきます。この骨の変化によって、当初はぴったりと合っていた入れ歯が徐々に合わなくなり、隙間が生じることで外れやすくなるのです。
特に総入れ歯を使用している方は、骨の変化が顕著に現れるため、注意が必要です。
入れ歯自体の経年劣化
入れ歯も長年使用するうちに、少しずつ変形や摩耗を起こします。特に咀嚼の力が加わることで、人工歯がすり減ったり、入れ歯本体がたわんだりすることがあるのです。このような変化が進むと、作製当初の精密なフィット感が失われ、外れやすくなります。
また、細かなヒビや傷が付くと、汚れがたまりやすくなります。これによって、口腔環境にも悪影響を及ぼすことがあるのです。
噛み合わせの変化
人間の噛み合わせは年齢や生活習慣によって少しずつ変化していきます。特に、残っている天然歯の位置が変わったり、周囲の歯が動いたりすることで、入れ歯との噛み合わせバランスが崩れることがあります。
噛み合わせが合わない状態で入れ歯を使用し続けると、部分的に過剰な力がかかり、入れ歯が浮きやすくなったり、外れやすくなったりするのです。
支えとなる歯や歯茎の状態悪化
部分入れ歯の場合、残存歯にバネを引っかけて固定するタイプが多く見られます。この支えとなる歯が虫歯や歯周病になり、進行すると、歯の動揺や歯茎の退縮が起こり、入れ歯の安定性が損なわれることがあります。
支えを失った入れ歯はぐらつきやすくなり、外れやすさが増すため、残存歯の健康管理も非常に重要です。
入れ歯の形や設計の問題
作製時の設計が使用者の口腔内に十分に合っていない場合、使用開始直後から違和感や不安定感が生じることがあります。特に、歯茎や骨の形状が特殊な場合には、通常の設計では適合しにくいケースもあり、個々に合わせた細かな調整が必要となります。
また、使用者の噛む力や咀嚼習慣に合っていない設計も、入れ歯のずれや外れの原因になります。
唾液の量や質の変化
唾液には入れ歯と粘膜の間の密着性を高める働きがあります。
しかし、加齢や服用している薬の副作用などによって唾液量が減少すると、入れ歯の吸着力が低下し、外れやすくなります。また、唾液の質が変化して粘り気が強くなる場合にも、滑らかに吸着できず安定性が損なわれることがあります。
唾液の状態は入れ歯の安定性に大きく関わるため、意識的に水分補給を行うことや、必要に応じて唾液分泌を促進することが重要です。
不適切な装着や使用方法
入れ歯の取り扱いに慣れていない場合、装着の仕方が不十分で、しっかりと吸着できていないケースもあります。また、硬いものを無理に噛んだり、食事の際に過剰な力を加えたりすると、入れ歯に無理な負荷がかかり、変形や破損のリスクが高まります。
入れ歯は正しく装着し、使用上の注意を守ることが、長く快適に使い続けるために重要です。
外れやすい入れ歯を使用し続けるリスク

合わない入れ歯を放置すると、さまざまな口腔内トラブルや全身の健康問題を引き起こす可能性があります。ここでは、外れやすい入れ歯を使い続けることで生じる主なリスクについて詳しく解説します。
咀嚼機能が低下する
入れ歯が安定していないと、十分に食べ物を噛み砕くことができず、咀嚼効率が著しく低下します。咀嚼が不十分なまま飲み込むと、消化器官に負担がかかり、消化不良や胃腸トラブルを引き起こす可能性があるでしょう。
また、硬いものや繊維質の多い食材を避けるようになり、栄養バランスが偏ることで、全身の健康にも悪影響を及ぼしかねません。特に高齢者の場合、食事内容の偏りはフレイルや認知症のリスクを高めるため注意が必要です。
顎の骨の吸収が進行する
入れ歯がしっかりフィットしていない状態が続くと、入れ歯の不安定な動きによって歯茎や顎の骨に不適切な圧力がかかります。この刺激が繰り返されることで、顎の骨の吸収が進みやすくなり、さらに入れ歯が合わなくなるという悪循環に陥ることがあるのです。
骨が痩せると入れ歯の安定性がさらに低下し、将来的には新しい入れ歯を作製する際にも調整が難しくなる可能性があります。
口内炎や粘膜の傷の原因になる
不安定な入れ歯を使用していると、食事や会話のたびに口腔内の粘膜をこすったり圧迫したりして、口内炎や潰瘍を引き起こすことがあります。特に入れ歯の縁が歯茎に食い込むような場合には、慢性的な傷ができやすく、細菌感染のリスクも高まります。
痛みや不快感があるとさらに入れ歯の使用を避けがちになり、食事量が減ったり社会生活に支障をきたしたりする可能性もあるでしょう。
発音や会話に支障が出る
入れ歯が外れやすい状態では、発音が不明瞭になりやすく、会話中に不意に外れることへの不安から、話すこと自体を控えるようになるケースもあります。コミュニケーションの機会が減ると、孤立感が強まり、精神的なストレスやうつ症状を招くこともあるかもしれません。
入れ歯がしっかり安定していることは、円滑なコミュニケーションを支えるうえでも非常に重要な要素です。
他の歯や組織への悪影響
残存歯にバネをかけて固定する部分入れ歯の場合、入れ歯がぐらついていると支えとなる歯に不均一な力が加わります。このような状態が続くと、健康だった歯が揺れたり、歯周病が進行したりして、最悪の場合には歯を失う可能性もあります。
また、無理に噛み合わせようとすると顎関節に負担がかかり、顎関節症の症状が現れることもあるでしょう。
入れ歯が外れるときはどうしたらいい?

入れ歯が外れたまま無理に使用を続けたり自己流で対処したりしようとすると、さらに状態を悪化させるおそれがあります。ここでは、入れ歯が外れるときに取るべき適切な対応について詳しく解説します。
無理に使い続けない
入れ歯が外れる原因には、入れ歯の変形や摩耗、顎の骨の変化などが考えられます。違和感や外れやすさを感じたまま無理に使用を続けると、歯茎を傷つけたり、さらにフィット感が悪化したりする可能性があります。
まずは無理に使い続けるのではなく、できるだけ使用を控え、必要最低限の場面での着用にとどめることが大切です。
歯科医院で診察を受ける
入れ歯が外れる場合、最も重要なのは早めに歯科医院を受診することです。歯科医師は、入れ歯の適合状態を確認し、必要に応じて調整や修理を行います。顎の骨の変化に合わせて入れ歯を調整することで、再びフィット感を取り戻すことができます。
また、部分入れ歯の場合には、支えとなる残存歯の状態もチェックし、必要に応じて治療を行うこともあります。
入れ歯安定剤を一時的に使用する
どうしてもすぐに歯科医院を受診できない場合には、市販の入れ歯安定剤を使用するのも一つの方法です。入れ歯安定剤を使用して、入れ歯と歯茎の間にクッションを作ることで、フィット感を一時的に高めることができます。
ただし、入れ歯安定剤の使用はあくまで応急処置であり、長期的な解決にはなりません。入れ歯安定剤を使っても違和感が続く場合や、痛みがある場合には速やかに歯科医師に相談しましょう。
生活習慣を見直す
入れ歯が外れる原因には、噛み方や食事内容も関係している場合があります。硬いものや粘着性のある食べ物を無理に噛むと、入れ歯に過度な力がかかり、外れやすさが増します。
違和感があるときは、なるべくやわらかい食事を心がけ、両側の歯でバランスよく噛むことを意識しましょう。また、無意識のうちに入れ歯を押す癖がある場合には、それも外れやすさにつながるため、意識的に避けることが重要です。
定期的なメンテナンスを習慣にする
入れ歯が外れるのを予防するためには、日頃から定期的にメンテナンスを受けることが欠かせません。歯茎や顎の骨は少しずつ変化するため、数年に一度は入れ歯を作り直したり、大幅な調整が必要になったりすることもあります。
定期検診では、入れ歯だけでなく、口腔内全体の健康状態もチェックしてもらえるため、トラブルの早期発見・早期対処につながります。長く快適に入れ歯を使い続けるためにも、半年に1回の頻度でメンテナンスを受けるとよいでしょう。
まとめ

入れ歯が外れる原因には、顎の骨の吸収、入れ歯の経年劣化、噛み合わせの変化、支えとなる歯や歯茎の状態悪化など、さまざまな要素が関与しています。
外れやすい入れ歯を使い続けると、咀嚼機能の低下や口内炎、顎の骨のさらなる吸収、発音障害などを引き起こすリスクが高まります。違和感を覚えたら無理に使用を続けず、早めに歯科医院で診察を受けることが大切です。
応急処置として入れ歯安定剤を使用する場合でも、調整や作り直しは必須となります。定期的なメンテナンスと適切なケアを心がけることで、快適な入れ歯生活を維持できます。
入れ歯を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。
当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。
投稿者
カテゴリ一覧
- さくらの山歯科クリニックブログ (414)
- 料金表 (1)
- 未分類 (24)
- 求人情報 (3)
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (4)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (3)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (4)
- 2020年5月 (5)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (1)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (3)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (4)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (3)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (6)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (3)
- 2016年6月 (3)
- 2016年5月 (5)
- 2016年4月 (3)
- 2016年3月 (4)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (5)
- 2015年11月 (5)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (3)
- 2015年6月 (3)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (3)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (3)
- 2014年7月 (3)
- 2014年6月 (4)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (5)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (2)